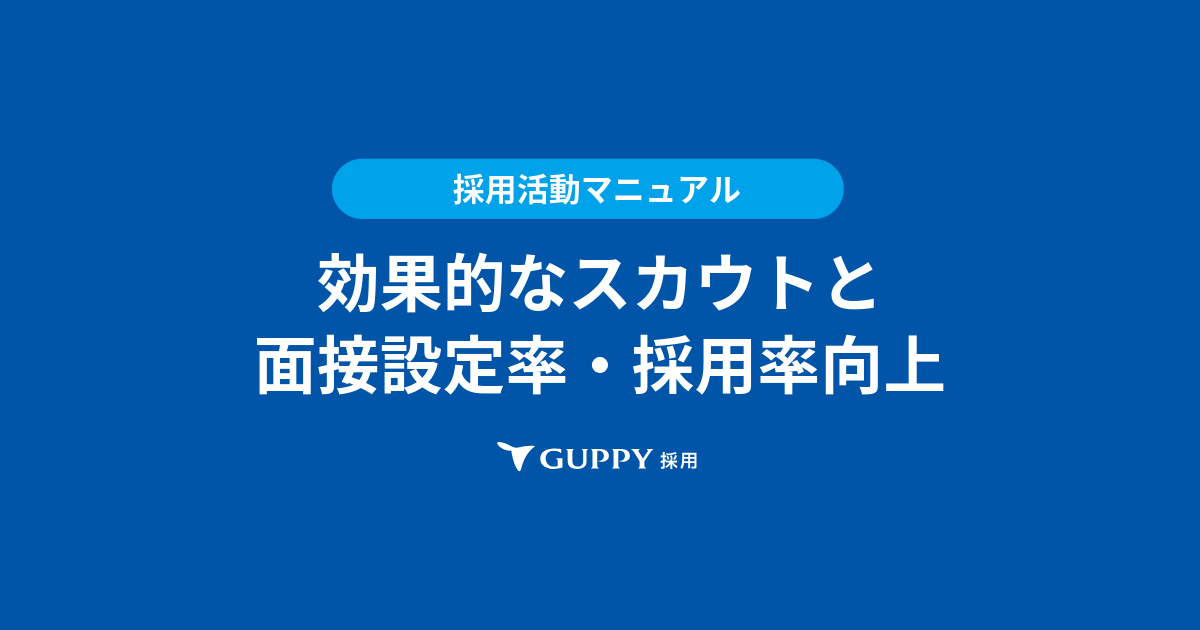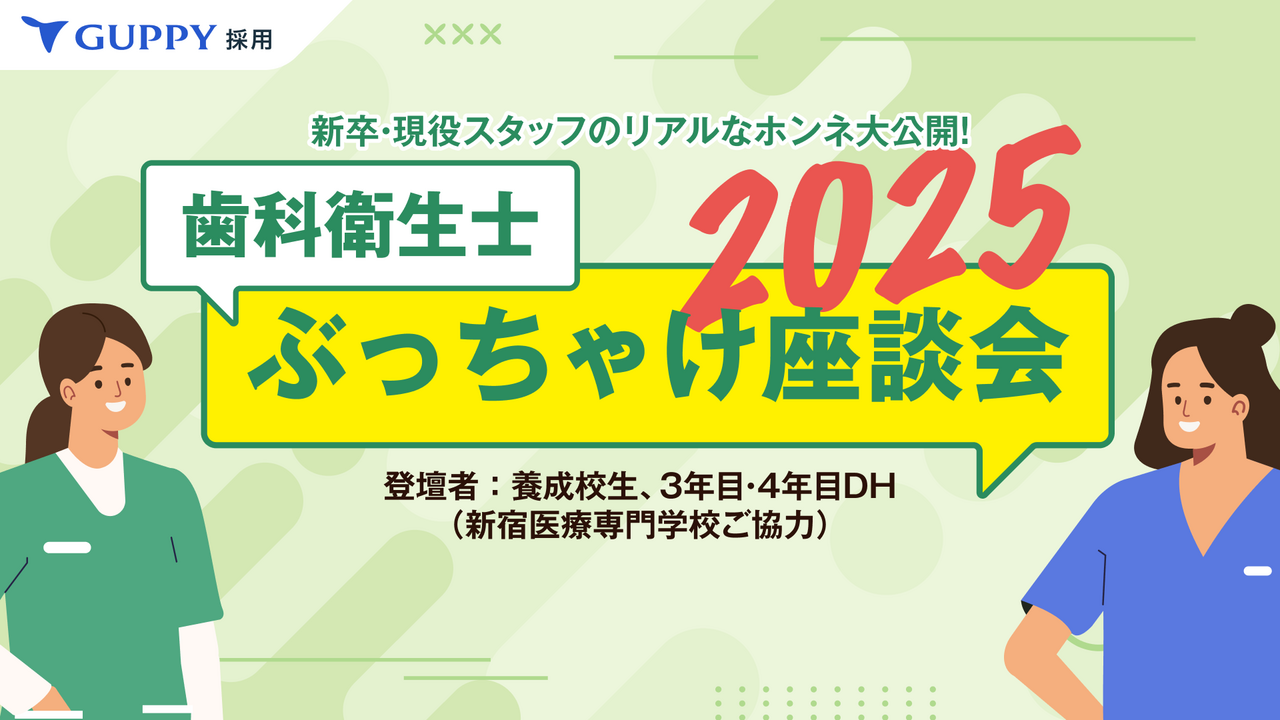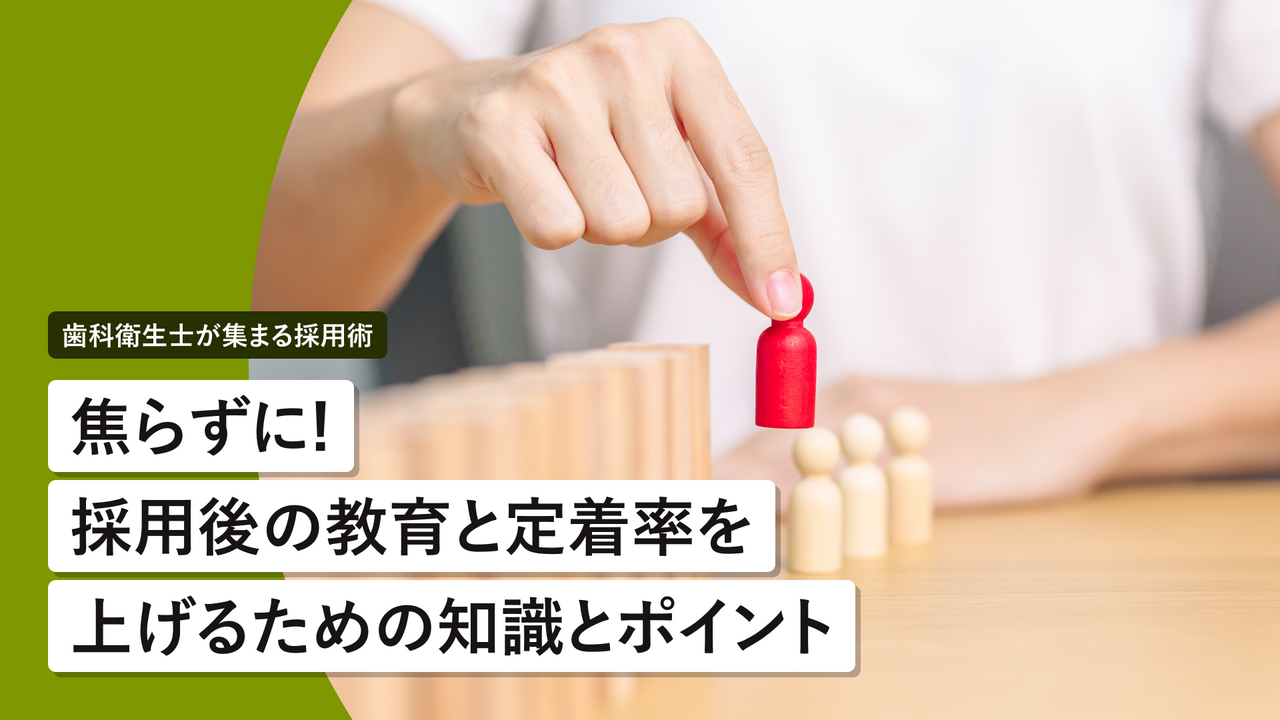
入職前後のおこりうるトラブル事例
人材採用を行っている中で、「応募が来ない」「採用が出来ない」といった事例の他にもトラブルが起こることがあります。今回は2つ、実際によく起こるトラブルをご紹介し、その原因と対策を解説します。
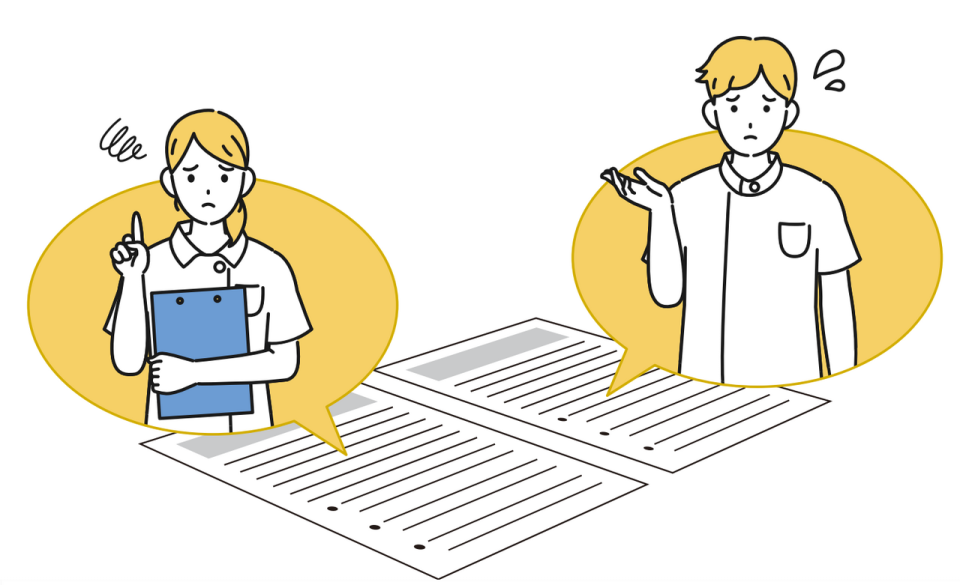
ケース①半年前に退職の申し出を受けた例
ご紹介する医院の状況はこうです。
前任者退職の申し出は退職希望の半年前にありましたが、求人情報は退職前月に掲載を開始しました。
掲載後、すぐに2件の応募があり、どちらも見学と面接を行うことが出来ました。
選考の結果、採用したかったのはAでしたが、在職中ですぐに入職することが出来なかったためBに内定を出し、前任歯科衛生士の退職1週間前に入職してもらうことになりました。
ここまでは順調でしたが、Bの入職後にトラブルが発生しました。
スタッフからBは「経験がないことは出来ないと、やろうとしない」「他のスタッフと関わろうとしない」「医院の文句ばかり言う」などの問題が露わになり、相談されるように。まだ入職して間もないから、としばらく様子を見ていると、Bが入社して1ヵ月で既存の歯科衛生士・歯科助手から退職の申し出があり、その後B本人も退職しました。結果としてスタッフは元々の人数よりも少なくなってしまいました。Bを採用していなければこのような事態にはならなかったかもしれません。
このケースでのポイントは次の3つ。
求人は速やかに掲載する
求人を出すのが遅かったこともあり、Aを断ることになっています。在職中の応募者も無理なく入職できるよう、スタッフから退職の申し出があった時点で速やかに求人を掲載する事が肝要です。
面接で応募者の本質を見極める
面接は、お互いの意向がマッチするか見定める貴重な場のため、雑談だけで終わらせずに、十分な時間をとって求職者のスキル・人柄・自院で活躍できるかどうかを把握することが必要です。見学時にはスタッフにもかかわってもらい、採用の合否もスタッフと相談して決めるのがベストでしょう。
入職後のトラブルは早期に発見・解決する
入職時には既存スタッフと十分なコミュニケーションを行い、スタッフ間で問題が発生したら、すぐ院長に相談できる環境づくりが必要となります。「新人だから」「入ったばかりだから」という理由から、様子を見た結果、他のスタッフにストレスや不満がたまってしまうのはよくありません。
ケース②応募は集まるが定着しない医院の例
次に、応募が多数集まる人気歯科医院にも関わらず、採用した人材が定着しないといった事例を紹介します。
求人を掲載後すぐに多数応募があり、既存スタッフの退職までにCが入職してくれたのでひと安心と思いきや、入職翌日に退職願が出された。理由は求人情報と実際の相違。
勤務終了時間が18時と書かれていたのに実際は19時半で、さらに社会保険完備とあったのに実際は未加入だったとのこと。
また、退職するスタッフがいることを知らなかったことも理由の1つだった。
このケースでは次の2つがポイントになってきます。
医院の実情をネガティブ面まで共有しておく
求人内容を間違えるミスは確実に避けるべきポイントです。
そして、当然のことではありますが、虚偽情報を書くことも法律で罰せられる可能性もあります。入職後トラブルがおこると、現代社会ではSNS等で噂が流れてしまい、今後の採用に影響することも考えられるため気を付けましょう。診療の合間の多忙な中で求人原稿を作成する事も多いかと思いますが、まずは、正しい情報を掲載することが何よりも重要です。
また、複数の求人サイトや、自院のHPに求人を掲載している場合は、内容が統一されているか定期的なチェックを行うことも重要なポイントになります。
条件・福利厚生面はしっかり伝えておく
労働条件通知書・雇用契約書を使い、条件面での認識に相違がないことを確認しましょう。
人材採用には悩みが尽きないとは思います。ですが、ひとつひとつ改善を行い、良い人材に長く働いてもらえるような院内環境を作りがポイントになります。
また、スタッフは院長に言いにくい不安や不満を抱えているスタッフもいるため、スタッフのメンタルマネジメントも医院経営には重要な意味を持ちます。スタッフと定期的な面談を設けること、朝礼など前向きな意見として発言する場をつくるなど、トラブル防止につながります。

記事を書いた人

医療機関、介護福祉施設等における人材採用や経営に関するお役立ち情報をお届けします。